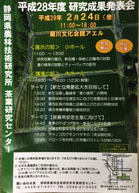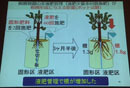Diaryカテゴリ
ショッピングカート
カートは空です。
商品カテゴリ一覧
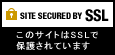
|
ホーム |
Diary
Diary
記事検索
Diary:313件
香る緑茶のスパゲッティ
秋の有機茶園
肥料工場の視察
微生物の勉強
エピガロカテキンガレート
有機栽培の粉末茶
お茶の成分に寿命を延ばす効果!
もう来年の茶づくりが始まっています!
有機栽培の粉末煎茶。これからの季節には冷茶で!
手摘み玉露
新茶で元気!
まだまだ新茶の収穫製造中!
新茶の状況
2017年新茶
新茶のご予約承り中!
2017年産の新茶
両河内の有機茶園
新茶前ほんやまの有機茶園
お茶の研究成果発表会
花粉にべにふうき
|