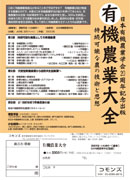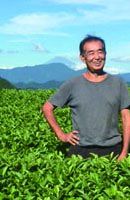Diaryカテゴリ
ショッピングカート
カートは空です。
商品カテゴリ一覧
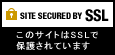
|
ホーム |
Diary
Diary
記事検索
Diary:313件
父の日におすすめの贈り物
新茶の粉末煎茶
一番茶の次は田植えです
一家でお茶刈り
りょうごうちの有機茶園
すけむねの有機茶園
新茶直前!生態系を守るお茶づくり
茶がらの佃煮
玉緑茶(ぐり茶)
免疫力を高めましょう
緑茶でうがい
スイスでお茶いれ
お茶とお花
あけましておめでとうございます
横浜で養生煎茶の試飲会
試飲会のご案内12月22日(日)
12月の有機茶園
有機農業大全
ウィーンでお茶会
秋の虫
|

 更になんと!土壌の下には磁場を組み、埋め込んでいます。養分の吸収には、土の粒子にプラスイオン、マイナスイオンの働きが関係してくるのすが、そういった働きを高めるための工夫です。
更になんと!土壌の下には磁場を組み、埋め込んでいます。養分の吸収には、土の粒子にプラスイオン、マイナスイオンの働きが関係してくるのすが、そういった働きを高めるための工夫です。