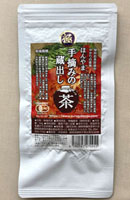Diaryカテゴリ
ショッピングカート
カートは空です。
商品カテゴリ一覧
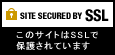
|
ホーム |
Diary
Diary
記事検索
Diary:313件
ティーペアリング
2月のほんやまの有機茶園
ほんやま1.5(イッテンゴ)
謹賀新年
ほんやま産の手摘みの熟成茶
常滑の窯元
和菓子が人気!スイスから
秋晴れの有機茶園
林金次語録~基本を尊ぶ~
静岡県のお茶の研究
有機栽培のミント緑茶
茶カテキンがコロナ不活性化に効果
紅茶の製造
遅れ芽
みどりの食料システム戦略
新茶を飲んで元気になりましょう!
ほんやまのお茶刈り
藤枝市すけむねの有機茶園
新茶の茶畑
今年は早い、新茶直前!
|