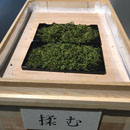Diaryカテゴリ
ショッピングカート
カートは空です。
商品カテゴリ一覧
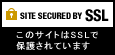
|
ホーム |
Diary
Diary
記事検索
Diary:313件
ご存じですか?4月8日はおからの日
家庭でできるアップサイクル食品
酒かす
お茶による新型コロナウィルスの不活化効果の研究に期待!
粉末の有機茶3種の焼き菓子
緑茶クッキー
あけましておめでとうございます
お茶の製造工程
お茶でコロナ無害化の研究
お茶と食べ物
11/30(月)本日、セミナー開催です
東京ハーヴェスト2020.開催中!
粉末ほうじ茶の試作
秋のお仕事
有機栽培のほうじ茶
オリエンタルグリーン
急須で作る冷たいお茶
お茶の葉の冷ややっこ
梅雨どきもおいしいお茶で爽やかに!
スマホサイト
|